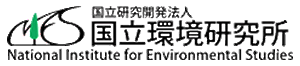資源循環・廃棄物処理におけるCCUS技術
2050年カーボンニュートラルに向けた廃棄物分野での対策の道筋
2020年10月に、日本は2050年までに温室効果ガス(GHG)の排出を全体として実質ゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。また、2021年4月には、日本は2030年度にGHGを2013年度比で46%の削減を目指すことを表明しました。これらの動きと時期を同じくして、国内の様々な分野で、カーボンニュートラルに向けた対策に関する議論がにわかに活発化しました。廃棄物分野でもそれは例外ではなく、環境省は廃棄物分野の2050年におけるカーボンニュートラルへ向けた具体的な道筋を示すため、2021年8月5日に中央環境審議会循環型社会部会で中長期シナリオ(案)(以下シナリオ案)を提示しました1)。

シナリオ案によると、日本における廃棄物分野のGHG排出量は、年間約4000万トン-CO2(2019年)で、排出源別では廃棄物の焼却及び原燃料利用(廃棄物を使った発電や熱回収、製品の製造用途への利用、廃棄物を原料として製造された燃料の利用等)に起因するGHG排出量が約8割を占めます。この4000万トン-CO2には、廃棄物の輸送、処理等の各段階で使用される燃料や電力の消費に起因するGHG排出量(エネルギー起源GHG排出量)は含まれていません。シナリオ案では、先述のGHG排出量4000万トン-CO2のうち、埋立、生物処理、焼却、原燃料利用に伴う3500万トン-CO2と、エネルギー起源GHG排出量のうち、廃棄物の収集運搬・中間処理(焼却・リサイクル等を指す)・埋立の各過程で使用される燃料や電力の消費に起因する900万トン-CO2(2019年)を対象として、これらを実質排出ゼロ化するための道筋を示しています。なお、廃棄物の原燃料利用は、素材産業等での原材料削減や化石資源由来のエネルギー利用等の削減に寄与しますが、そういった効果(他分野におけるGHG削減効果)はシナリオ案では加味されていません。シナリオ案で掲げられている複数の重点対策は、①製品素材のライフサイクルを通じた脱炭素化、②脱炭素型廃棄物処理システム、③廃棄物処理施設・車両等の脱炭素化の3つの方向性でくくられています。イノベーションが起きる可能性も考慮に入れた上で、これらの対策を最大限に実施した場合に、2050年において年間GHG排出量はマイナス、つまり年間998万トン-CO2のGHG吸収量となる試算が示されています。この試算において、対策ごとのGHG削減量の内訳をみると、CCUSの効果が年間1,614万トン-CO2と見積もられています。CCUSは二酸化炭素の回収・利用・貯留技術のことで、シナリオ案では焼却施設から発生するCO2の90%を回収して貯留した場合のGHG削減量をCCUSの効果として計上しています。試算ではGHG排出量をマイナスとしていましたが、ちょうどゼロにする場合でも、約600万トン-CO2のCCUSによるGHG削減効果が必要であることになります。廃棄物分野におけるCCUSの本格的な技術開発や実用化展開は、まだ始まったばかりといえます。今後、この技術を実現していくための廃棄物処理システムの変革は、廃棄物分野の2050年カーボンニュートラルに向けた課題の一つとされています。
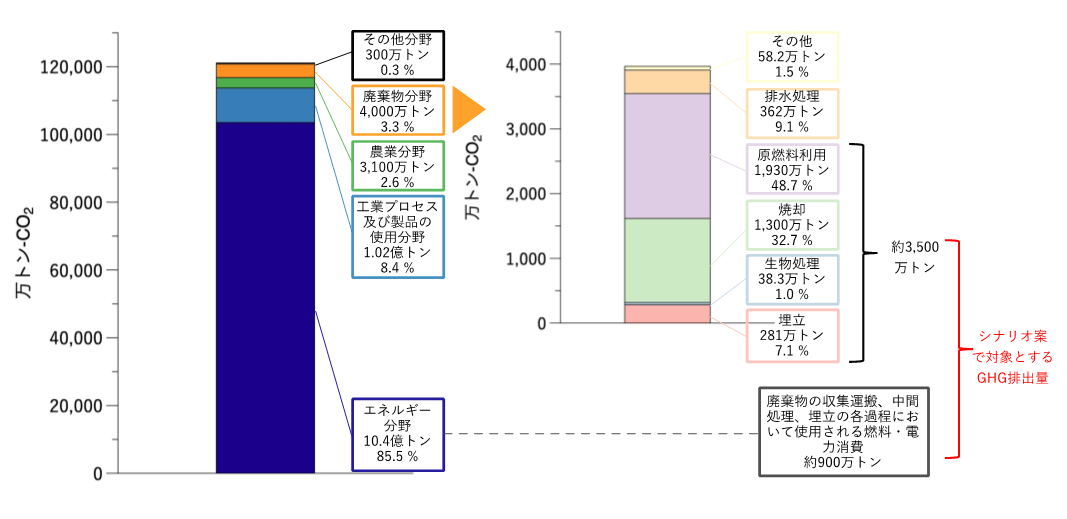
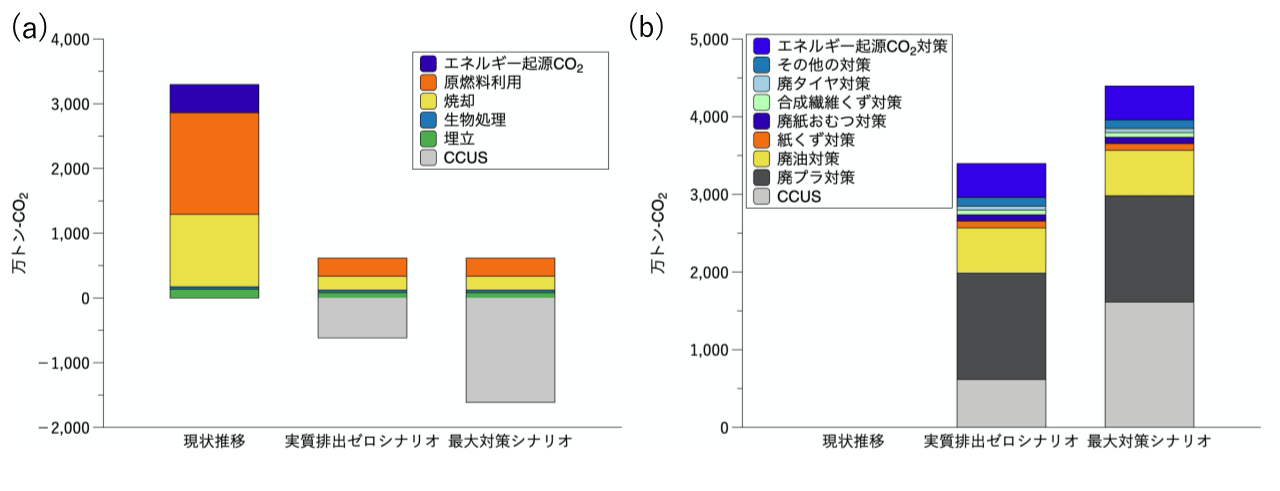
資源循環・廃棄物処理におけるCCUS技術の導入
カーボンニュートラルな社会における廃棄物を対象としたCCUS技術の役割は、廃棄物の徹底した発生抑制・再使用と、製品素材毎の原料への再利用等に取り組んだ上で、残った廃棄物を中間処理する際に発生するCO2を燃料・素材等へリサイクルしたり、地中等へ貯留したりすることです。廃棄物の中間処理のうち、減容化(量を減らし、安定化させること)技術には大きく分けて熱処理と生物処理の2方式があり、熱処理には焼却、熱分解・ガス化等の技術が、生物処理にはメタン発酵、堆肥化等の技術があります。図3は、こうした中間処理の技術とCCUS技術の各方式を組み合わせたシステムの経路を示しています。CCUSは以下の要素技術から構成されます。すなわち、①廃棄物処理に伴う生成ガスの処理、②生成ガスからのCO2の分離・回収、③CO2を貯留・利用する場所への輸送、④CO2の素材・燃料等への変換または貯留です。例外的に、①、②の段階を省いて、廃棄物処理の生成物を直接燃料等へ変換する技術もあります。これまでに様々な要素技術が提案されていますが、それぞれの技術の成熟度は基礎研究段階のものから商用化されている技術まで様々です。①に関するガスの処理や、③に関するパイプライン技術は商用化レベルです。②、④に関しては、非常に幅広い種類の技術が存在していますが、成熟した水準にあるものはごくわずかです。その中で、焼却排ガス中CO2の化学吸収及び炭酸飲料や植物工場での利用が商用化レベルの技術といえます。
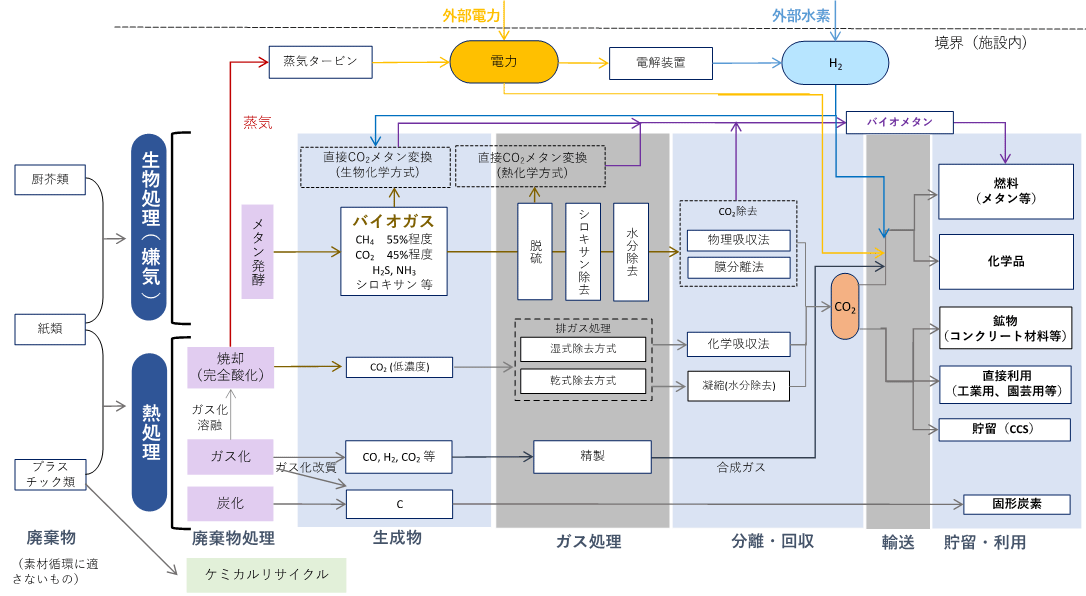

具体的な技術の例として、国内外の廃棄物処理施設で実装ないし実証が確認できているプロセスを図4に示しました。図4(a)は、焼却排ガスからCO2を分離・回収し、回収後の高純度CO2ガスを植物工場等で利用するプロセスです。焼却排ガスには7〜12%程度のCO2が含まれています。ガスは高温かつ不純物を含みますので、冷却・洗浄工程を経てCO2回収設備へと導入されます。排ガスからのCO2回収法には高圧下で水に接触させて吸収させる方式、CO2を選択的に透過する膜を通して分離する方式、溶剤に対して化学的にCO2を吸収させる方式等様々ありますが、流入ガスの圧力、CO2濃度、回収後のガスのCO2純度等の条件に応じて適した方式が選択されます。現在のところ、稼働中の焼却施設では、CO2濃度が比較的低い排ガスの処理に適した化学吸収法が適用されています。化学吸収法では、まず前段の吸収塔においてCO2を吸収しやすいアミン溶液と排ガスとの接触によってCO2をアミン溶液に吸収させ、後段の吸収液再生塔では、リボイラに蒸気を供給することで吸収液を加熱し、CO2ガスをアミン溶液から分離させます。このようにして回収された高純度のCO2は用途に応じた要求水準まで後処理設備で精製され、利用されることになります。プロセスを通して、排ガス中のCO2の90%ほどが除去され、ごみ1トンあたりから、1トン程度のCO2が回収されます。吸収設備は1日あたり数十トン〜数百トンのCO2を分離する処理能力を持っています。焼却排ガス中に含まれるSOxやHClは、化学吸収液であるアミン溶液を劣化させることから、排ガスを吸収塔へ導入する前にこれらを除去することが重要となります。また、吸収液再生塔でリボイラを稼働させるために大量の熱エネルギーが必要なことも課題とされています。こうした課題に対応して、最近では吸収液の長寿命化や、エネルギー効率の高いプロセスの開発が進められています。なお、回収側だけでなく、焼却側でもCO2濃度を高めるための燃焼技術開発も取り組まれています。一方、図4(b)は、厨芥類等の、主に食品くずからなる有機性廃棄物の生物処理と発生ガス中のCO2のメタン変換を組み合わせたプロセスで、欧州でいくつかの実証例があります。CO2のメタンへの変換は、触媒を用いる熱化学的処理と微生物を用いる生物化学的処理があり、両技術とも実証段階の水準です。熱化学的処理は、発電施設や焼却施設からの排ガスを含む広い排ガスを対象として技術開発が進められているのに対し、生物化学的処理は専らバイオガスを対象として進められており、図4(b)に示しているのは生物化学的処理です。厨芥類等を発酵タンクを使って酸素のない条件下で微生物と接触・反応させたときに発生するガスには50〜60%程度のメタンと40〜50%程度のCO2が含まれます。これをバイオガスと言い、国内ではバイオガスを発電に利用する取り組みが広がり始めていますが、図4(b)に示したプロセスではCO2をさらにメタンへと変換することで天然ガスに近い組成の高濃度のメタンを製造することを目的としています。2050年のカーボンニュートラルに向けては、アンモニアや水素のような次世代燃料の利用が進むことが予想されていますが、インフラ整備に必要な投資の大きさが障壁となり、全てのガス燃料がこれらに置き換えられることは実現困難であるとされています。カーボンニュートラルな方法で製造されるメタンは、既存インフラを活用しながら脱炭素化へ貢献できることから、利用の拡大が期待されています2)。CO2メタン変換を行う生物化学的処理として最も一般的なものは、微生物とガスとの接触の効率を高めるようにデザインされた反応装置に、バイオガスとそれに含まれるCO2物質量の4倍量の水素を導入し、微生物の関与の下に水素とCO2からメタンと水を合成する(4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O)方式です。この方式は、ガスの前処理が必要ないという特徴を持っているので、発酵タンクと一体型で有機物の分解・ガス化とCO2のメタン化を同時に進行させる技術もあります。プロセスを通して、厨芥類1トンあたりから、150〜200 Nm3程度のメタンが生成されます。生成されたメタンの利用先の一例として、都市ガス導管に注入する際には、ガス中の不純物を除去した上で、単位体積あたりの熱量を一定の水準まで調整したり、ガスへ臭いを付加する必要があります。
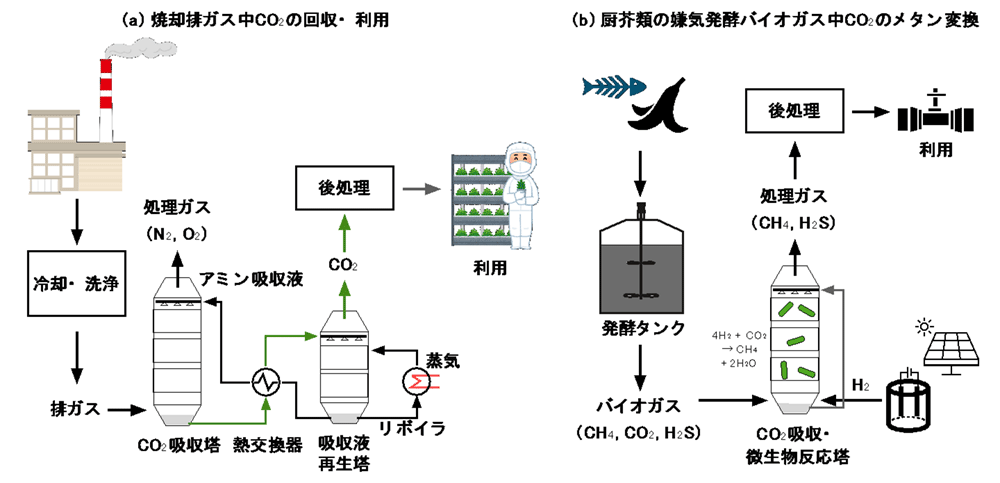
このように、廃棄物を対象としたCCUSの要素技術の中には、完成までの展望が開けてきつつあるものがあります。しかしながら、既存の廃棄物中間処理施設の更新や新設に伴って、こうした技術を導入していき、冒頭に述べた年間約600万トン-CO2の削減を達成していく具体的な見通しは立っていません。特に課題として取り上げられるのは産業やインフラとの連携と施設立地の問題です。回収されたCO2やそれを変換して製造される化学品、燃料は、それを製造・利用する産業やインフラとの連携が必要で、その効率は処理施設と連携先の立地に依存します。また、前述のCO2分離・回収技術には規模のメリットが働くため、小規模になるほど投資・運転コストが割高になる傾向があります。日本では、現状で一般廃棄物の80%は焼却を中心とした熱処理によって中間処理されていますが、全国に焼却施設は1100施設ほど存在し、その約半分が処理能力100トン/日未満の中小規模施設、うち190施設ほどは処理能力30トン/日未満です3)。また、そうした中小規模施設は離島、中山間地域に特に集中しています4)。このような事情から、単純にごみ処理施設の付帯設備としてCCUS技術を整備していくだけでは、期待通りのCO2削減の効果が得られない恐れがあります。今後、焼却施設と連携したCCUSの取組を推進するためには、施設の更新時期を踏まえながら、上述の連携等を加味したごみ焼却の広域処理・大規模化への移行が必要になってくると思われます。一方で、そのような広域化が難しい場合には、焼却と比較して小規模でも廃棄物から直接エネルギー等を回収可能でCO2発生量も少ない熱分解・ガス化やメタン発酵といった中間処理法と、CCUSとを組み合わせた技術を新たに開発し、地域でのCO2を含めた資源循環を行なっていくのが有効な手段の一つであると考えられます。