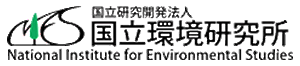排水処理に広がる嫌気性膜分離技術
嫌気性膜分離(AnMBR)法とは
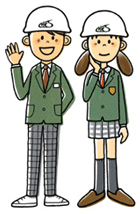
生物学的水処理法には、酸素を必要とする好気性処理法と、酸素を必要としない嫌気性処理法があります。嫌気性処理は、水中の有機物をメタンと二酸化炭素にまで分解できる優れた排水処理技術です。この方法は省エネルギーであり、しかもメタンガスの回収によりエネルギー生産が可能、余剰汚泥の発生量が少ないなどの利点があるため、これまで比較的高濃度の溶解性有機性排水処理に広く適用されてきました。しかし、この方法は低濃度の産業排水や生活排水を処理する場合、嫌気性微生物の維持・増殖に大きなコストがかかるため、経済的に適用できません。また、嫌気性処理単独では処理水質が放流基準を満たすレベルになく、好気性などの後処理が必要になります。そうした背景の下、嫌気性処理の適用範囲を拡大するためには、微生物を高濃度に保持することと、処理水質の向上が可能な技術の開発が求められてきました。これらを同時に達成できる手段として、嫌気性処理と膜分離技術を組み合わせた嫌気性膜分離法 (AnMBR: Anaerobic membrane bioreactor) が、近年世界的に試みられるようになってきています。AnMBRは嫌気条件の反応槽内に導入されたろ過膜により排水中で固液分離を行い、槽内に保持できた嫌気性微生物により有機物を分解する生物的な排水処理方法です。
AnMBR法の歴史
1978年、Grethleinが初めて嫌気性消化槽の後段に膜技術を追加しました。膜技術とは、μm~nm(10-6~10-9m)規模の細孔を有する水処理用の特殊な膜で、水の中から細孔を通り抜けることのできない不純物を除去する技術です。これによって処理水の生化学的酸素要求量(BOD)と硝酸塩はそれぞれ、85-95%と72%と、高い除去率に達しました。約40年間の発展に伴い、AnMBRシステムの利点は様々な研究文献で十分に証明されています。AnMBRの価値を認識した民間会社と各国政府はAnMBRシステムを促進するためにかなりの投資を行いました。1980年代に、嫌気性膜分離システム(Membrane Anaerobic Reactor System (MARS))と嫌気性限外ろ過システム(Anaerobic Digestion Ultra filtration (ADUF))が最も注目を集めた技術であり、実工業排水の処理にも応用されました。日本においては、経済産業省が行った1986年のアクアルネッサンス'90が最初のプロジェクトであり、その後、1991年から厚生労働省による水道用浄水分野の共同研究開発「MAC21」や「膜式し尿処理」、「膜式合併浄化処理の開発研究」などのプロジェクトにおいて大規模に研究が実施され、様々な膜分離方法や排水について研究が行われました。1990年代終わりに株式会社クボタによって生ごみ処理向けの浸漬型AnMBR(Submerged Anaerobic Membrane Bioreactor (SAMBR))が開発され、その後同社の「KSAMBR」という浸漬型AnMBR技術が食品・飲料産業排水分野にも普及がはじまりました。クボタ社の他にはカナダのADI社とオランダのBiothane社などの会社もAnMBRの開発を加速しています。
AnMBR法の特徴
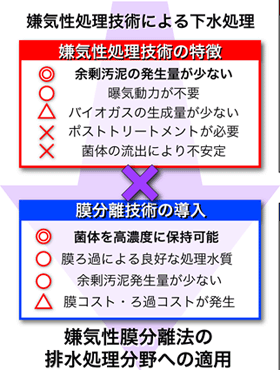
AnMBRは、嫌気性処理とMBR技術の利点を兼ね備えています。MBR技術とは微生物より小さい孔径を有する分離膜で反応槽外への微生物の流出を完全に防止するものであり、MBR技術の導入で微生物より小さい孔径を有する精密ろ過膜(Micro Filtration:MF)により槽外への微生物の流出を完全に防止することができるため、菌体を高濃度に保持が可能です。また、膜ろ過による良好な処理水質が得られます。一方、AnMBRは嫌気性処理として曝気不要で従来の活性汚泥法より省エネです。また、処理過程に生成したバイオガスがエネルギーとして回収できます。最後に、汚泥発生量がすくないため、ランニングコストの低減が期待されます(図1)。
AnMBR法を用いた排水処理
近年、AnMBR法を用いた排水処理に関する研究が数多く行われています。工場排水について、高濃度有機物を含有している製紙、繊維、乳製品、石油化学、魚加工など様々な排水では、AnMBR法は従来法より良い処理水質が得られると報告されています。報告されたAnMBR法の中に、AnMBR処理は食品工業排水の特性に非常に適しているため、最も応用されています。一般的に、有機物負荷が2~15 kg-COD/m3/dの範囲では、その食品工場排水のCOD除去効率は90%以上に維持できます。一方、有機物濃度が低い生活排水に対して、従来は嫌気性処理よりも好気性処理の方が適していると考えられてきましたが、最近になって、AnMBRを用いた嫌気性処理単独での下水処理の可能性を実験的に検討したことも報告されています。その結果、図2に示したように、AnMBR法は活性汚泥法と比べて高いエネルギー回収率および低い汚泥生成量の利点を持つため、下水処理への適用も期待されています。従って、AnMBRは理論的にほとんどの排水処理に適しているようであり、高い処理率と処理水質を達成できる技術です。
図2に示したように、AnMBR法は従来の処理法と比べ、処理システムの簡素化、バイオガスから回収できるエネルギー(電力量)が高く、排出する廃棄物(消化汚泥)が少ないとの利点を持つことが明らかになりました。
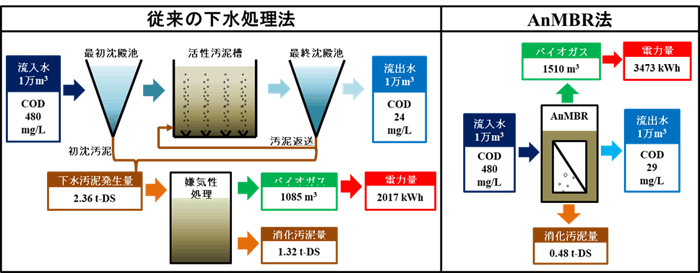
今後の展望
AnMBRを用いた排水処理に関する研究の大半はベンチスケールの実験に限定されています。多くの場合、ベンチテストの結果は、実排水にアプリケーションには単純に移行することはできないので、より多くのフルスケール研究が必要となります。コスト面から見ると、膜が目詰まりしてしまう(膜ファウリング(Fouling))ことは依然としてAnMBRの運転コストと長期間メンテナンスに影響する最も重要な要因です。より効果的かつ簡単な方法で膜ファウリングを最小限に抑えることが今後重要な研究課題です。また、AnMBRで採用されている膜はコストが高い有機高分子材質が圧倒的に多く、膜材質の最適化がシステム全体のコストダウンに寄与することが期待されています。処理効果の面から見ると、AnMBRは高いBOD、CODおよびSS処理率が得られる一方、窒素、リンの除去率が低いため、後処理が求められています。