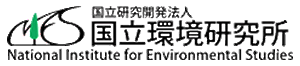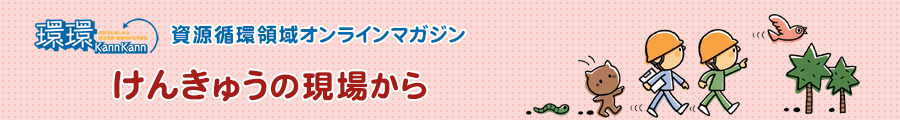
将来の可燃ごみと生物乾燥の実証実験
将来の可燃ごみの処理

日本では今後、多くの地域で人口減少と少子高齢化が進行すると予測され、それらはごみの量と質に影響します。人口が減少すると、ごみの排出量も減少します。また、少子高齢化が進行すると、子供用の使用済み紙おむつの排出量が減少する一方で、大人用の使用済み紙おむつの排出量が増加します。さらに、SDGs、サーキュラー・エコノミー(循環経済)、地域循環共生圏、脱炭素社会などの将来ビジョンの達成に向けて、様々な取組が行われることによって、将来の可燃ごみの組成が大きく変化する可能性があります。
これまで、日本における主要なごみ処理技術は焼却処理でした。焼却処理は大規模であればあるほど効率的に処理することが可能なごみ処理技術です。今後、人口が大幅に減少する地域ではごみの排出量も大幅に減少するわけで、そのような地域では稼働率やエネルギー効率の観点で焼却処理が非効率になってしまうことも考えられます。そのため、将来のごみの量や質の変化に対応できる処理技術が必要です。ところで、焼却処理以外の可燃ごみの処理技術として、生物乾燥という技術があります。生物乾燥とは、酸素を十分に供給した状態で可燃ごみを一定期間、積み置き、微生物に生ごみなどを分解させて、その際に生じる発酵熱を使って可燃ごみを乾燥させる技術です。生物乾燥後は金属類や不燃物を機械で取り除き、生成した可燃物を燃料として製紙工場などで利用することができます。生物乾燥は、小規模でも稼働することができ、可燃ごみが保有しているエネルギーを焼却処理よりも効率的に利用できる処理技術であると言えます。この可燃ごみの生物乾燥を日本で唯一実施しているのが香川県三豊市にある株式会社エコマスターです。我々研究チームは、同市と同社のご協力により、将来的に可燃ごみの組成が大幅に変化しても生物乾燥が問題なく適用できるかどうかを実証してみました。
可燃ごみの生物乾燥の実証実験

生物乾燥の実証実験は、株式会社エコマスターがイタリアから取り寄せた長さ5.7 m、幅2.3 m、高さ1.5 m(20 m3)の実証槽を用いて行いました(写真2)。この実証槽に可燃ごみ、発酵補助材(種ごみ)、構造材(木くず)を2:1:1の比率で投入する必要があったのですが、試料のかさ密度を0.4トン/m3として計算した結果、可燃ごみ3.5トン、発酵補助材1.75トン、構造材1.75トンの試料を投入することになりました。我々研究チームは、将来の可燃ごみの組成変化を予測し、その組成を模擬したごみを準備しました。将来の可燃ごみの組成変化を予測する際には、大人用の使用済み紙おむつが増加したり、可燃ごみ中のプラスチック類が大幅に減少したりするシナリオを立ててみました。模擬ごみを準備するために、香川県三豊市で収集された可燃ごみを9区分(紙類、使用済み紙おむつ、布類、プラスチック類、ゴム・皮革類、木・竹・わら類、厨芥類、不燃物、その他)に分類し、必要重量に至るまで各区分のごみを集めるという作業を行いました(写真1)。作業者は防護服、ゴーグル、防塵マスクなどを装着して新型コロナウイルス感染症の感染対策を取り、懸命にごみの分類と計量作業を行ったのですが、どうしても必要重量が足りない紙おむつに関しては、介護施設などから別途収集した使用済み紙おむつで補充しました。3.5トンのごみの分類、計量作業は、ごみの調査研究の中でも最大級の規模で、本当に大変な作業でした。
続いて、準備した模擬ごみを機械で破砕してから発酵補助材と構造材とともに混合し、実証槽に投入しました(写真2)。実証槽は上部のみが開閉する構造でしたので、試料をクレーン車で吊り上げて上部から実証槽に投入しました(写真3)。実証実験は雪が舞う真冬の屋外で実施しましたので、生物乾燥の初期段階でうまく試料の温度が上がるか、つまり微生物がちゃんと活動してくれるかが少々不安でした。しかし、無事に試料の温度が上がったことを確認でき、可燃ごみの組成が大幅に変化しても生物乾燥が適用できることを実証することができました。
今後自治体は、盲目的に可燃ごみの焼却処理を維持するのではなく、それぞれの地域課題を踏まえ、また地域特性を活かして、焼却処理以外の可燃ごみの処理技術を模索すべきであると考えます。特に人口減少・高齢化が進行する地域では、生物乾燥が焼却処理にとって代わる主要な処理技術になり得るかも知れません。