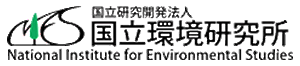本ページについて
ページ最終更新日:2025年12月5日
1.格納されているデータについて
環境省が毎年調査している一般廃棄物処理実態調査のデータを格納しています。この実態調査データは、1970年代から長年調査されてきた世界的にみても貴重な廃棄物統計データです。その有効な活用のため、国立研究開発法人国立環境研究所 資源循環領域では、その調査結果をアーカイブデータとして整備し、「一般廃棄物長期時系列データ閲覧システム」などとして公開してきました。本データは、さらに近年のデータならびに施設データを追加し、自治体支援ツール(データビジュアライゼーションのページ)として公表するものです。
これまでの施設のデータは時系列データとして経年変化をみることができなかったのですが、その経年変化が閲覧でき、また、全国の類似する市町村との比較が行えることなどが本支援ツールの特徴となっています。
- 一般廃棄物には、ごみとし尿が含まれますが、本ページで対象としているのは「ごみ」のデータのみです。
- アーカイブデータのうち、市町村のデータが多く存在するのが1990年度以降ですので、1990年度以降のデータを格納しています(データの更新・修正の履歴はこちら)。また、東京23区のデータは各区のデータよりも23区合計のデータの方が充実しているので、23区合計のデータを格納しています。
- ごみの処理は、市区町村だけでなく、複数の自治体で協力して一部事務組合など(以下、「事務組合」という。)を設立し、事務組合が処理事業を行っている場合があります。この際の事務組合のデータの扱いですが、ごみの量のデータ(リサイクル率などの量の割合のデータも含む)は、そのごみがどこ自治体から来たものかという由来にしたがって、元の自治体の量のデータに割り当てられています。
- 市町村合併前のデータについては、現在の市町村を構成する旧市町村のデータを総和したデータを格納しています。
- 広域ブロックについては、2019年に公表した一般焼却施設および粗大ごみ処理施設の施設集約検討に向けた地図データの作成の際に収集・整理したデータを用いています。それ以降のブロック更新の情報は反映されていませんので、ご注意ください。
- 施設のデータについては、現存する施設(データの最新年度に存在している施設)のみを格納しています。すでに廃止されている施設のデータはみることはできません。
- ごみの総排出量と総資源化量は、次のように定義されます。
(総排出量)=(収集量)+(直接搬入量)+(集団回収量)
(総資源化量)=(直接資源化量)+(中間処理後再生利用量)+(集団回収量) - ごみ排出原単位(1人1日当たりのごみ排出量)やリサイクル率のように割り算を用いて算出するデータは、2021年度以降のデータを除き、すべて再計算して値を算出しています。そのため、公表されている統計データとは一致しないデータが若干ある可能性があります(その場合は、公表データの算出が間違っているか、算出に用いる公表データに間違いがあるかのどちらかであると考えられます)。市町村合併前のデータについては、算出式の分子と分母でそれぞれ総和を行ったうえで、割り算を行って算出したデータを格納しています。
用いた算出式は以下のとおりです(環境省の算出式と同じ)。
(ごみ排出原単位)=(総排出量)/{(総人口)×(年間日数(365もしくは366))}
(リサイクル率)=(総資源化量)/{(総処理量)+(集団回収量)}
ただし、1990年度と1995年度のリサイクル率は、データの制約があり、次式で近似値を算出しています。
(リサイクル率)=(総資源化量)/(総排出量) - ごみ排出原単位は、現在、環境省では、生活系、家庭系、事業系に区別して値を公表しています。
これらの種類別の排出量は次のように定義されます。生活系ごみと事業系ごみとに大別されたうえで、生活系ごみについては資源ごみを除いたものを家庭系ごみと称しています。
(総排出量)=(生活系ごみ排出量)+(事業系ごみ排出量)
(家庭系ごみ(※資源ごみを除く)排出量)=(生活系ごみ排出量)-(集団回収量)-(生活系資源ごみ収集量)
-(生活系直接搬入ごみのうち資源ごみの量)
しかしながら、「家庭系ごみ」と「生活系ごみ」との混同や、「ごみ」という用語において資源ごみを含むものとそうでないものがあるという分かりにくさがあることから、本ページでは「家庭系ごみ」は「生活系非資源ごみ」と呼び変えるとともに、事業系の非資源ごみについてもデータを格納しました。それぞれ定義式は次のとおりです。
(生活系非資源ごみ排出量)=(家庭系ごみ排出量)
(事業系非資源ごみ排出量)=(事業系ごみ排出量)-(事業系資源ごみ収集量)
-(事業系直接搬入ごみのうち資源ごみの量) - 処理・処分に関するデータは、次のような定義です。
処理量は、環境省の実態調査の定義に基づき、次式で表されます(法律上、最終処分は「処理」の内訳です)。
(処理量)=(直接焼却量)+(焼却以外の中間処理量)+(直接最終処分量)+(直接資源化量)
一方、中間処理後に発生する処理残渣の焼却や最終処分があり、実際に施設で処理・処分される量は、上記の「処理量」の値とは異なります。
(総焼却量)=(直接焼却量)+(焼却以外の中間処理による処理残渣の焼却量)
(最終処分量)=(直接最終処分量)+(全ての中間処理による処理残渣の最終処分量) - 大分類として、「建設改良費」「処理及び維持管理費」「その他費用」の3つの費目が調査されており、さらに細目での費用が調査されています(建設改良費については「収集運搬施設の工事費」「中間処理施設の工事費」「調査費」など、処理及び維持管理費については収集運搬や中間処理などの事業活動ごとに「人件費」「処理費」「委託費」などの細目があります)。
- 建設改良費とその他費用は年変動が大きく、処理及び維持管理費は比較的安定することから、①これら3つの費用を総和した総費用と②処理及び維持管理費のデータを格納しました。また、これらの一人当たりの費用のデータも格納しました。
- また、本サイトでは、事務組合のデータは格納せずに、事務組合を構成する市町村にごみの量や費用を割り戻してデータを整理しています。これは、人口などの社会経済関係のデータとごみ量や処理費用量との関係を理解しやすくすることと、市町村レベルにおいてもごみ処理にかかるフルコストを理解しやすくするためです。そこで、本サイトの市町村の費用データには、各市町村の組合負担金が含まれています。この扱いをを明確にするため、組合分を含む費用の名称を「総・・・費用」としました。
- 以上のことをまとめ、式で表すと次のとおりです。
(市町村の総費用)=(市町村の総建設改良費)+(市町村の総処理及び維持管理費)+(市町村のその他費用)
(市町村の総建設改良費)=(市町村の建設改良費)+(建設改良費に係る組合分担金)
(市町村の総処理及び維持管理費)=(市町村の処理及び維持管理費)+(処理及び維持管理費に係る組合分担金) - 他方、現在の一般廃棄物実態調査では、各市町村と各事務組合に対し細費目レベルでの調査がされています。そのため、細目レベルでも全国や都道府県などの費用集計ができるようになっています。また、全国と都道府県のデータにおいてはフルコストで計上されています。式で表すと次のとおりです。
(全国の総費用)=Σ(都道府県の総費用)
(都道府県の総費用)=Σ(市町村の各費用の合計(組合分担金を含まない)+Σ(事務組合の各費用合計)
(都道府県の各費用)=Σ(市町村の各費用(組合分担金を含まない)+Σ(事務組合の各費用)
本サイトでは、上記の式で定義される全国と都道府県の総費用と処理及び維持管理費のデータを格納しました。 - 留意点としては、組合分担金の数式上の扱いが全国・都道府県レベルと市町村レベルで違うことです。なお、事務組合においては、市町村からの分担金以外にも、使用料や地方債などで運営資金を獲得しており、そこからの支出もあります。そのため、本サイトにおける「都道府県の総費用」と「当該都道府県内の市町村の総費用の合計」は必ずしも一致しません。
- 施設データで、格納されている施設種は、焼却施設、粗大ごみ処理施設、資源化施設(堆肥化施設を含む)、燃料化施設、リサイクルプラザ、保管施設、その他処理施設、最終処分場です。
- 施設の使用年数は、現時点から施設の稼働年までの年数として算出しました。
- 施設の稼働率は、次式を用いて算出しました。この式は、連続運転をする焼却施設については多用されていますが、他の施設は1週間における計画稼働日数が5日だったり、1日における計画稼働時間が8時間に満たないなど、施設の運転計画が異なります。あくまでも標準化された参考値として認識ください。
(稼働率)=(処理量[トン])/{(施設容量[トン/日])×290日)}
ただし、粗大ごみ破砕施設の調整係数には、平日のみの稼働を想定して、さらに5/7を乗じた。
また、保管施設とストックヤード、リサイクルプラザの稼働率は算出しなかった。
なお、稼働率が0となった場合はゼロデータを格納せずに、データなしとした。 - 最終処分場の場合は、稼働率ではなく、次式の残余割合を算出しました。
(残余割合)=(残余容量[m3])/(全体容積[m3]) - 広域化ブロックの区割りは、現在、各都道府県で見直しが検討されています。本データベースにおいては、2019年に公表した一般焼却施設および粗大ごみ処理施設の施設集約検討に向けた地図データの作成の際に収集・整理した独自の「施設集約検討ブロック」のデータを用いました。1997年度と2006年度において得られた各都道府県の広域化計画の情報をもとに設定したものであり、当時、再検討中であったり、広域化ブロックが明確にされてこなかった場合でも、施設集約の検討を促すために、独自にブロックを設定したものです。最新の情報は反映されていませんので、ご注意ください。
- 各都道府県において、最新の広域化ブロックが策定されましたら更新していく予定です。もし、最新情報をお持ちでしたら、新しい広域化・施設集約計画のURL情報などとともに、下記連絡先までお知らせいただければ幸いです。
- 本ページには、一般廃棄物処理実態調査のデータ以外にも、各市町村の高齢化率や財政力指数のデータも格納しています。これらの定義等は下記のとおりです。
(高齢化率[%])=(65歳以上の人口)/(総人口)×100 ※5年ごとの国勢調査で把握される。
(財政力指数)=(基準財政収入額)/ (基準財政需要額) ※過去3年間の平均値として算出される。東京都23区の指数は各区の指数の単純平均値。
財政力指数が高いほど、財源に余裕があるといえます。なお、東京都特別区(23区)の財政力指数は、東京都の算出に基づいており、他団体の財政力指数とは算出方法が異なります。詳しくはこちらデータの異常値について
こちらのページをご覧ください。
データ全般
自治体の処理状況に関するデータ
費用に関するデータ
施設に関するデータ
広域化ブロックに関するデータ
社会経済関係のデータ
2.未来シミュレーターの計算方法について
-
以下に示す式で、各パラメータの算出を行っています。複数の自治体を選択した場合には、複数の自治体を対象として算出が行われます。
将来のごみ排出量
(将来t年度の総排出量(対策なし))=(将来の人口)×(年間日数)×(現在のごみ排出原単位)(将来t年度の総排出量(対策あり))=(t年度の総排出量予測(対策なし))×{1-(t年度のごみ減量率)}
・将来の人口には、国立社会保障・人口問題研究所(2023)「日本の地域別将来推計人口」を用いました。
・この将来推計において、福島県「浜通り地域」はまとめて推計が行われているため、本シミュレーターでもまとめた状態で計算を行っています。なお、浜通り地域とは、いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の13市町村です。
・東京23区は、一つの地域としてまとめた状態で算出が行われます。
ごみ減量率は、次式で定義されます。
(t年度のごみ減量率)={(現在のごみ排出原単位)-(t年度のごみ排出原単位)}/(現在のごみ排出原単位)
ごみ減量対策が行われた場合のごみ減量率は、次式で算出されます。つまり、2050年度まで直線的に、ごみ減量が進みます。
(将来t年度のごみ減量率)=(2050年度のごみ減量率目標)×{t-(対策開始年度)}/{2050-(対策開始年度)}
将来の資源化(リサイクル)量
(将来t年度の総資源化量(対策なし))=(t年度の総排出量予測(対策なし))×(現在の資源化率)(将来t年度の総資源化量(対策あり))=(t年度の総排出量予測(対策あり))
×{(現在の資源化率)+(t年度の追加資源化率)}
・追加資源化率は、2030年度から2050年度まで、5年おきに設定できます。ただし、0≦(将来のリサイクル率)≦100% となるように設定しなければなりません。
・続く段落に示す総焼却量もしくは総最終処分量の算出において、それらの値が負となるために0と修正された場合は、追加資源化率はそれぞれ次の式で算出される追加資源化率の値に置き換えられます。
(将来t年度の追加資源化率)=(現在の総焼却量)/{(現在の総排出量)×(焼却削減貢献割合)}
(将来t年度の追加資源化率)=(現在の総最終処分量)×(t年度の総排出量予測)/[(現在の総排出量)
×(t年度の総排出量予測)×{1-0.95×(焼却削減貢献割合)}]
※なお、実績データがある年度も「排出量×資源化率」で算出される総資源化量の値を表示させたため、一般廃棄物実態調査データとわずかに値が異なることにご留意ください(排出と処理の時間差によるもので「排出量≒処理量+集団回収量」であるため)。
将来の焼却量
(将来t年度の総焼却量(対策なし))=(現在の総焼却量)×(t年度の総排出量予測(対策なし))/(現在の総排出量)
(将来t年度の総焼却量(対策あり))=(現在の総焼却量)×(t年度の総排出量予測(対策あり))
/(現在の総排出量)
-(t年度の総排出量予測(対策あり))×(t年の追加資源化率)×(焼却削減貢献割合)
ただし、(将来t年度の総焼却量)が負の値の場合は、0とします。
・「焼却削減貢献割合」は、新たに追加する資源化によって焼却処理される廃棄物量が減る割合です。デフォルト値は100%としています。新たに追加する資源化が、直接埋立されていたモノや処理後残渣(焼却灰など)の資源化を対象とする場合には、この割合を小さくしてください。資源化率をより大きく設定しても、焼却量が減らないように計算がされます。
将来の焼却施設の稼働率と必要な焼却施設容量
焼却施設の稼働率は、環境省の計算式をもとに次式で算出されます。(焼却施設の総稼働率)=(対象自治体が用いる施設の合計焼却量予測[トン])
/{(対象自治体が用いる施設の合計施設容量[トン/日])×290日}
未来シミュレーターでは、現存する焼却施設の合計施設容量を維持した場合の施設稼働率を表示します。
新規施設の規模を検討する際に、どの程度の縮小が必要かの参考にしてください。
また、将来に必要となる焼却施設容量は、次式で算出されます。つまり、上記定義における施設の稼働率を100%としています。
(t年度に必要な焼却施設容量[トン/日])=(t年度の合計焼却量予測[トン])/290日
なお、一部事務組合の施設のように複数の自治体が用いる施設の場合、ユーザーが選択した以外の自治体の焼却量もこれらの数式の分子の「合計焼却量予測」に含めています。ユーザーが選択した自治体の場合は、人口変化と追加対策を考慮した場合の焼却量を用いていますが、選択していない自治体の場合は、追加対策は考慮せず、人口変化のみを考慮した焼却量を用いています。ただし、複数の自治体の使用割合が大きく偏っている施設の場合など、値が正確でない場合があります。
将来の最終処分量
(将来t年度の総最終処分量(対策なし))=(t年度の総排出量予測(対策なし))×(現在の総最終処分量)/(現在の総排出量)
(将来t年度の総最終処分量(対策あり))=(t年度の総排出量予測(対策あり))
×[(現在の総最終処分量)/(現在の総排出量)-(t年の追加資源化率)×{1-0.95×(焼却削減貢献割合)}]
ただし、(将来t年度の総最終処分量)が負の値の場合は、0とします。
なお、右辺の0.95は、焼却ごみの一般的な残渣率である5%を想定して設定されています。
また、
(埋立容積[m3/年])=(埋立廃棄物重量[トン/年])×(覆土比)
であり、覆土比は、実態調査データの外れ値を除いて対数平均を求め、1.07m3/トン(n=675)と設定しています。
設定した条件でエラー表示がでる場合
「ユーザーが設定した追加リサイクル率が実現できない年度があります。」と表示される場合は、下記の点の設定を見直してください。表示されている結果は適切なものではなく、使うことはできません。1)設定した「追加リサイクル率」と最新年度のリサイクル率」を足すと100%を越える年度はありませんか。あれば、追加リサイクル率の設定を見直してください。
2)なければ、「焼却削減貢献割合」が小さすぎます。直接最終処分をされている廃棄物の量以上に、追加のリサイクルを行おうとしています。設定した「焼却削減貢献割合」を大きくしてください。
3.グラフ等の操作方法について
-
本ページにおけるグラフや地図は、一つ前の状態や最初の状態に戻すことができます。全画面で表示させることもできます。
また、本ページのグラフや地図は、画像ファイル、PDFファイル、パワーポイントのファイルとしてダウンロードが可能です。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
4.推奨引用について
- 例えば、次のように引用ください。
- 国立環境研究所、一般廃棄物データビジュアライゼーション:自治体支援ツール、 http://www-cycle.nies.go.jp/jp/db/file01/visualize00.html (○○年○○月○○日アクセス)
- 国立環境研究所、一般廃棄物未来シミュレーター、 http://www-cycle.nies.go.jp/jp/db/file01/visualize51.html (○○年○○月○○日アクセス)
5.作成者等
5.問い合わせ先
- 国立研究開発法人国立環境研究所 資源循環領域
- e-mail: J-Waste-DB_info(末尾に@nies.go.jpをつけてください)
なお、個々の調査データについての質問には回答できかねます。データビジュアライゼーションのページ作成および二次情報としてデータ整備を行ったことについてのみ回答させていただきますこと、ご承知おきください。