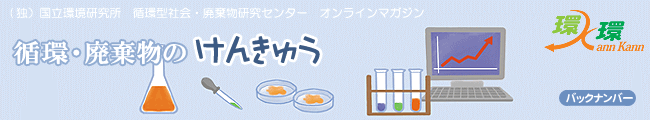
ごみの熱分解・ガス化による生成物の特性とその有効利用
私たちが日常生活から排出しているごみは色々なものが混ざっている混合物です。例えば、可燃ごみをいくつかの物質に分類してみると、生ごみ、紙、繊維、木材、プラスチック、ゴム/皮革類などが主な成分になっています。この中で、石油から製造された化学繊維、合成ゴム、プラスチック類を除けば、2008年11月17日号「廃棄物系バイオマス」で説明したように、その他の可燃ごみはほぼ生物由来のバイオマスに該当することがわかります。したがって、私たちが排出している燃えるごみは、多くのバイオマスとプラスチックのような石油由来の物質から成っていると言えます。現在、これらの燃えるごみは、"燃える"という言葉が意味しているように焼却によって処理されています。焼却は、有機物を完全燃焼するのに必要な理論空気量より過剰の空気を吹き込んで燃やすことによって最終的にCO2等の酸化ガスやH2O等に分解させる方法です。これは発熱反応なので発生した燃焼熱はお湯や電気として利用されます。一方、焼却時に発生したガスは様々な酸性ガスや微量汚染物質を含んでいるので大気中に排出するためには、規制に定められている物質を一定濃度以下まで処理しなければなりません。

もし、空気供給を遮断した状態で加熱すると、このような燃えるごみはどうなるのでしょうか。反応温度などによって、生成物の量と組成は異なると思いますが、基本的に気相、液相、固相の生成物が得られます。前述した焼却の場合、CO2などの酸化ガス、水、焼却残渣(灰分)が生成物となりますが、空気を遮断した状態で加熱すると、水素、一酸化炭素、メタン、炭化水素類などの可燃ガス、粘性のある黒褐色の油成分であるタール、それから炭に似たようなチャーというものが生成します(2009年2月23日号「ごみから炭作りができる?」参照)。一般的にこのような反応を熱分解と言いますが、ここに適量の水蒸気などを反応器内に注入すると、チャーと水蒸気の間の反応が促進されることによって可燃ガスの生成量がさらに多くなります。このような反応をガス化反応と言います(2007年1月22日号「熱分解ガス化」、2008年11月17日号「ガス化―改質技術による廃棄物系バイオマスからのエネルギー回収」参照)。これを可燃ごみに適用すれば、熱だけではなく、燃料あるいは材料としての利用が可能になります。
ここで私たちは燃えるごみの主な成分であるバイオマスと石油由来の代表物質であるプラスチック類の割合が異なる三つのごみを試料として用意しました。バイオマス100%の廃木材チップ、バイオマスとプラスチックの割合が各々 9:1と 7:3であるRDF(Refuse Derived Fuel)とRPF(Refuse Paper & Plastic Fuel)を500〜900℃の反応器内に入れ、空気の代わりに窒素ガスを注入した熱分解条件と窒素ガスとともに微量の水蒸気を注入したガス化条件により得られた生成物の量と組成などを調べました。以下、その実験結果を簡単に紹介します。
図1に 各処理条件におけるごみ単位重量当りに得られたチャーの収率を示します。熱分解条件では、原料中の炭素と灰分がチャーとして多く残りますが、温度が高くなるほどチャーの収率は緩やかに減少します。得られたチャーの発熱量は、廃木材チップのチャーが29〜31 MJ/kg、RDFチャーが15〜18 MJ/kg、RPFチャーが18〜19 MJ/kgであり、 石炭あるいは木炭(発熱量13〜30 MJ/kg)の代替燃料として利用できることが分かりました。一方、窒素と水蒸気を注入したガス化条件の場合、700〜900℃まで温度が上がると、ガス化反応が進み、チャーの収率が急激に低下します。しかし、この温度域で得られた廃木材チャーの場合は、約900 m2/gの比表面積を持ち、吸着能の高い活性炭の比表面積に匹敵するものであることが分かりました。したがって、これらの反応によって得られたチャーは燃料あるいは吸着材として利用できる可能性があります。
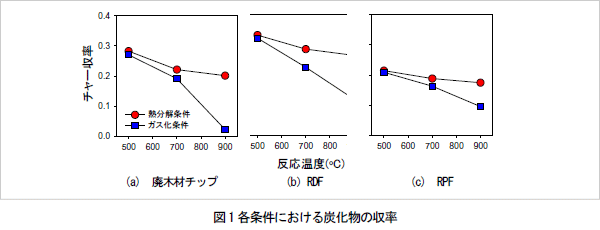
図2には、各処理条件において、試料1 kg当りに得られたガス量とその組成を示しています。熱分解条件では、ガス生成量が少ないが、ガス化反応条件になると、反応温度が上昇することによりガス量が多くなり、さらに、H2とCOガスの割合が多くなることが分かります。これら結果から原料中炭素量を1とした場合に、チャーまたは可燃ガスとして回収された炭素量を推計すると、図3のようになります。低温の熱分解条件では、チャーとして炭素が回収され、高温でのガス化反応では、可燃ガスとしての炭素回収率が高くなることが分かります。廃木材チップとRDFの場合は、原料の中で炭素がチャーあるいはガスの形として最大8割まで回収されますが、RPFの場合は、比較的炭素回収率が低く、7割以下となります。これは多くの炭素分がチャーとガスではなく、タールになってしまうということです。副生物であるタールは、配管の閉塞や後段の発電プロセスなど生成ガス利用プロセスに対してさまざまな阻害を与える物質なのであまり望ましくありません。特に低温条件でRPFから生成されたタールには、長い直鎖系の炭化水素類の割合が高く、分子量が大きいものが分解されずに多く残っていることが確認されました。
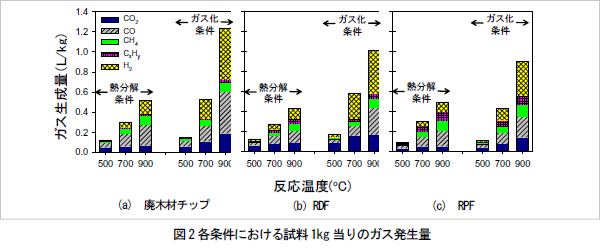
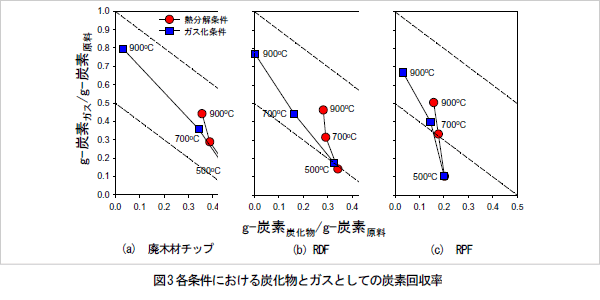
このように各条件による生成物の物質収支、組成、炭素回収率などを把握することによって、木質系バイオマスは、低温条件での熱分解によるチャーとしての回収、または、高温条件でのガス化反応による水素や可燃ガスとしての転換利用の利便性が大きいものと考えられました。一方、ごみ中のプラスチック成分が多いほどタール発生が多く、チャーあるいはガスとしての利用可能性は低くなることがわかりました。したがって、熱分解・ガス化による有効利用を進める場合は、より高温でのガス化反応や高性能のタール分解触媒の使用を考慮しなければならないと考えられます。
<もっと専門的に知りたい人は>
- 黄仁姫、川本克也:C2-1バイオマス・プラスチック系廃棄物の熱分解・ガス化反応における生成物の物質収支および基礎特性、第20回廃棄物資源循環学会研究発表会公演論文集、CD−ROM、2009.
