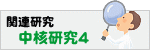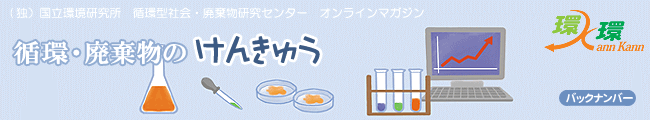
アジアのごみ処理で発生する温室効果ガスをより正確に推計する
 気候変動に影響を与えるとされている二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスについて、排出量を削減するための様々な試みが行われています。その基礎データとして、各国はその温室効果ガス排出量を報告書としてまとめ、国連に報告することになっており、日本は毎年これを報告しています。この数値は、京都議定書などで定められる削減目標の設定、達成の確認などに用いられるものです。ですから、報告書に記載される排出量をより正確に推計することは、とても重要なことです。しかし同時に、それは大変難しいことです。我々の生活や産業に関わるすべての活動が、逐一監視され、その都度排出される温室効果ガスが計測されるような世の中であれば、すべてを足し算すれば正確な排出量が求められます。でもそれはムリな事ですし、何より息苦しい社会です。従って今のところは、活動の指標となる数値(化石資源の消費量、廃棄物の焼却量など)に対して、その活動単位ごとに発生すると考えられる温室効果ガスの代表値を掛け算することで、温室効果ガスの排出量が求められています。こうした代表値のことを「排出係数」といいます。
気候変動に影響を与えるとされている二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスについて、排出量を削減するための様々な試みが行われています。その基礎データとして、各国はその温室効果ガス排出量を報告書としてまとめ、国連に報告することになっており、日本は毎年これを報告しています。この数値は、京都議定書などで定められる削減目標の設定、達成の確認などに用いられるものです。ですから、報告書に記載される排出量をより正確に推計することは、とても重要なことです。しかし同時に、それは大変難しいことです。我々の生活や産業に関わるすべての活動が、逐一監視され、その都度排出される温室効果ガスが計測されるような世の中であれば、すべてを足し算すれば正確な排出量が求められます。でもそれはムリな事ですし、何より息苦しい社会です。従って今のところは、活動の指標となる数値(化石資源の消費量、廃棄物の焼却量など)に対して、その活動単位ごとに発生すると考えられる温室効果ガスの代表値を掛け算することで、温室効果ガスの排出量が求められています。こうした代表値のことを「排出係数」といいます。
温室効果ガスの排出原理が同じであっても、国や地域によって排出係数が異なる場合があります。たとえば、同じ量の重油を燃焼させて発生する二酸化炭素量は同じだとしても、メタンや一酸化二窒素の排出量は燃焼の状況や廃ガス処理の状況によって排出係数が異なります。我が国では、ほとんどの産業活動で実態に即した独自の排出係数を用いていますが、すべての国がそのようなことができるわけではありません。そこで国際機関が、さまざまな活動における排出係数の代表値を作成しており、独自の排出係数を持たない場合は、そちらを使用して温室効果ガスの排出量を算定してもよいことになっています。もちろん実情にあった排出量であるに越したことはないわけですから、その改善のための様々な取り組みがなされています。国立環境研究所では、地球環境研究センターがアジア途上国の排出量算定の支援に取り組んでいるほか、我々のグループではごみ処理の分野を対象として、排出係数の精緻化や新たなカテゴリーの提案に向けた作業と情報共有のための会議を開催しています。
ごみ処理の分野では、ごみを埋め立てる活動、ごみを燃やす活動、ならびにごみを生物的に処理する活動などからの温室効果ガス排出を算定することとなっています。我が国ではそれぞれ、最終処分場、焼却施設、ならびに堆肥化施設などが排出源にあたります。途上国の多くでは、「ごみの投棄地」、「野焼き」が、我が国の最終処分場、焼却施設に相当する排出源となります。特にごみの集積投棄は埋立地とさえ呼べないような劣悪な環境を生み出し、景観上の問題だけでなく、感染症の温床や悪臭の発生源となり、崩壊の危険性もあります。健康や安全の観点からも重要なこうした問題を解決する努力をしている途上国に対して、我が国も様々な形で支援して、より安全で衛生的な最終処分場への転換を図っています(2010年5月24日号「途上国のゴミ捨て場の改善に関する研究」参照)。
埋立地から排出される温室効果ガスの成分は「メタン」で、酸素のない状態で有機物が微生物に分解されて発生することがわかっています。皮肉なことに、埋立地からの悪臭や病害虫獣を防ぐために土をかぶせて、大気と遮断することでかえってメタンが発生しやすい状態になってしまいます。この際の排出挙動は、今年埋めたごみが今年中にすべてメタンになる、というような簡単なものではなく、何十年とかけてゆっくりと分解され、メタンが発生しつづけます。いつどのくらいのメタンが出るのかは、ごみの分解速度とガスへの転換率で決まりますが、こうした排出係数についてアジア途上国に特有の数値はまだ少なく、欧米や日本など気候帯の異なる地域の数値を代用したり、不確実性の高い数値を用いたりしています。我々は現地調査や室内実験を元に、こうした排出係数について精度の高い数値を提案しています。一般的に使用されているごみの分解速度(半減期として4.1年)を用いた場合と比べて、我々の提案した分解速度(半減期として2.1年)を採用した場合、最大で24%も排出量が変わる可能性があることからも、実情にあった排出量算定が必要であることが理解できるでしょう。
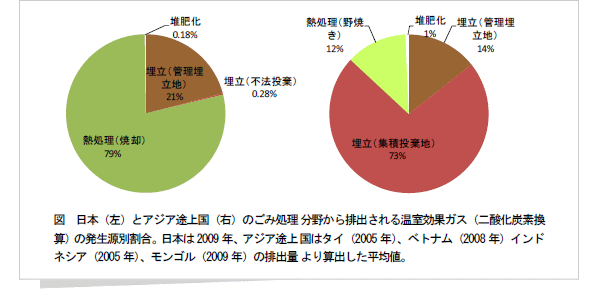
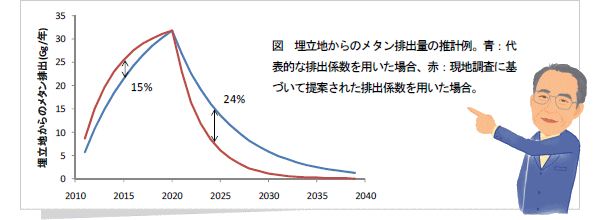
温室効果ガス排出量の把握や対策が進まなければ、いつの日か個人が「温室効果ガスカウンター」を携帯することを義務づけられ、排出量の多い人は罰せられてしまうような社会がくるかもしれませんね。私たちが、精度の高い排出係数を一刻も早く世の中に提供することができれば、そのような必要性はなくなるかもしれません。もちろんそれと同時に、皆さんの排出削減努力がそのような社会の到来を防ぐことにつながっています。
<もっと専門的に知りたい人は>
- Ishigaki, T. et al.: Estimation and field measurement of methane emission from waste landfill in Hanoi, Vietnam, Journal of Material Cycles and Waste Management, 10(2), pp.165-172, 2008
- Wangyao, K. et al.: Methane generation rate constant in tropical landfill, Journal of Sustainable Energy and Environment, 1(4), pp.159-163, 2010