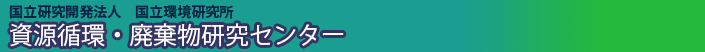| プラスチックの処理・リサイクル技術 |
| マテリアルリサイクル [技術の概要] |
|
|
| 技術概要 |
- プラスチックのマテリアルリサイクルは、鉄、アルミ、ガラスや紙に比べて難しい。
プラスチックが単一な素材ではなく、ポリエチレン、ポリプロピレンなど多種類の樹脂が存在するため、原料としてリサイクルするためには同一の種類のものを多量に集める必要がある。
このため、プラスチックのリサイクルには破砕、選別、洗浄、乾燥などの前処理技術が必要であり、再生した原料がどの程度の価値を有するかは、この前処理技術に大きく依存することになる。
- 前処理技術は
①切断・破砕・粉砕 ②分離・分別 ③洗浄 ④脱水・乾燥 ⑤配合・混合
の5段階に分けることができる。
|
| ① |
切断・破砕・粉砕 |
一般的に「切断」は数cmから数十cm程度に分割切断する操作、「破砕」は数cmの粗い粒度に砕く操作、「粉砕」は数mm程度の粒度に砕く操作と言われている。
切断・破砕・粉砕を行うことで、表面積の拡大による処理の速度と均一化の促進、その後の処理にける粒径・粒度に対する要求への対応、プリント基板などの複合材における組成の分離、体積の減少、流動性の付与、水分の低減・均一化などの効果が期待される。
破砕方法には乾式破砕・湿式破砕・水中破砕という分類、冷凍破砕・常温破砕・温熱破砕・溶融状破砕という分類があるが、廃棄物処理においては一般的に常温乾式破砕が採用されている。 |
| ② |
分離・分別 |
廃プラスチックの再生においては、産業系の単一でまとまった原料が得られる場合を除き、排出源・グレード、品質レベルが明確でなく、前処理として分離・分別が必要とされる。
破砕された廃プラスチックの混合物を種類別に分離・分別するには比重、風力、静電気などの物理的・機械的な手法が用いられる。
一方、材質の識別には比重などのほか、X線、近赤外線などの光学的手法が多く用いられる。分離・分別方法の選定にあたっては、リサイクルの方法、製品の品質レベル及びコスト要因にマッチした方法を選ぶ必要がある。 |
| ③ |
洗浄 |
廃プラスチックには土砂や薬品、食品かす等で汚れているものがあることから洗浄が必要となる。
求める品質や汚れの種類によって洗浄の方式は異なってくる。
単なる水洗であることもあるが、温水にしたり、洗剤や中和剤を加えたりすることもある。
洗浄の方式はバッチ式と連続式があるが、いずれの場合も排水の処理が問題となる。 |
| ④ |
脱水・乾燥 |
洗浄されたプラスチック片には水分が付着しているため、乾燥機に直接供給しないで、あらかじめ脱水しておく必要がある。
脱水の方式としては、主として遠心脱水方式(バッチ式、連続式)が使用される。
プラスチックに水分が含まれていると、加熱溶融時に溶融能力を低下させるだけでなく、再生品の内部発泡の原因にもなるので、十分乾燥させておく必要がある。
乾燥方式としては熱風乾燥方式が主である。
乾燥機にはいろいろなタイプのもがあるが、一般には気流乾燥機がよく使用されている。 |
| ⑤ |
配合・混合 |
再生品の所要の物性に適合したプラスチック組成を得るために数種のプラスチックを配合することがある。
また添加剤を配合する場合もある。
また、配合した後にプラスチックを混合したり、顔料や安定剤、充填材などを均一に混合することもある。 |
|
|
- 以上に述べたような前処理を終えた廃プラスチックを再生するわけであるが、再生方法は内容によって単純再生と複合再生に分けることができる。
- 単純再生とは、単一の廃プラスチックをペレット化あるいは粉砕などによってプラスチック原料として再生することであり、原料としては工程のグレード規格外品や流通残品など汚れが少なく着色されていても種類別に明確に分別されているものが対象となる。
これらはそのまま成形加工工程に投入されることもある。
- 生産工程端材・副産材・市場廃棄・回収品など単純再生に回せない廃プラスチックについては複合再生が必要となる。
複合再生の場合には原料となる廃プラスチックの組成をより均質化させるために、成形される製品の用途・要求に適したなんらかの配合・混練を行うことが一般的である。
以下にプラスチック再生の一般的なフローを示す。
|
樹脂選定 |
|
複合再生の場合はMI・比重・引張り・破断等の物性確認 |
↓ |
|
|
計量ホッパ |
|
充填材・添加剤や各種の助剤・顔料等の配合比率を決める |
↓ |
|
|
配合ホッパ |
|
ミキシング処理(ヘンシェルミキサー等) |
↓ |
|
|
押出機 |
|
ペレタイジング装置(押出機=単軸・2軸・多軸) |
↓ |
|
|
冷却装置 |
|
水冷(水槽・シャワー=チラ-ユニットで水温管理) |
↓ |
|
|
切断カッター |
|
空中切断(ロータリー式・円盤式等) |
↓ |
|
|
選別ふるい装置 |
|
(3mm標準にてふるい選別) |
↓ |
|
|
ストッカー |
|
フレコン袋・タンク缶等 |
↓ |
|
|
タンブリング |
|
装置(ロット単位のペレットをさらに均質化) |
↓ |
|
|
搬送装置 |
|
可動ホッパ・フィーダー・各種コンベア・リフト・ターレット等
|
↓ |
|
|
一次成形加工 |
|
成形工程へ |
| 出典:(社)プラスチック処理促進協会「プラスチックリサイクル便覧」(2000) |
|
| |
- また、プラスチック製容器包装の材料リサイクル施設については、以下の4タイプに大別される。
|
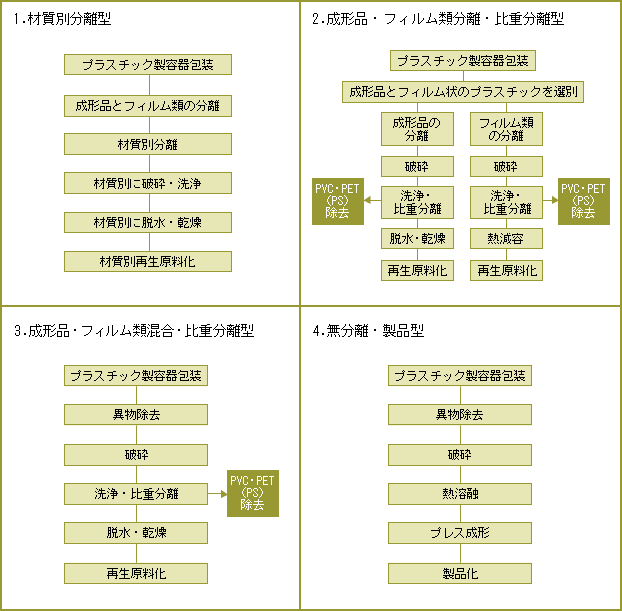
図 プラスチック製容器包装の材料リサイクル施設の分類 |
| 出典:厚生省「容器包装リサイクルシステム推進事業報告書」(2000) 一部加筆 |
|
| マテリアルフローにおける位置付け、受入実績 |
- マテリアルリサイクル(材料リサイクル)は、容器包装リサイクル法における再商品化手法として、平成16年度には、プラスチック製容器包装再商品化量の18.4%に相当する5.7万tの再商品化を行っている。
(再商品化に占める割合は平成12年の13.3%から年々増加している)
- なお、産業系の廃プラスチックについては、2004年で135万tがマテリアルリサイクル(再生利用)されているとの報告がある。
((社)プラスチック処理促進協会)
|
|
| 受入可能な廃プラスチック |
- 容器包装リサイクル法におけるプラスチック製容器包装の材料リサイクルにおいては分別基準適合物を対象としている。
- 廃プラスチックに混入している塩ビについては、マテリアルリサイクルの際の障害となる場合もある。
|
| 受入能力 |
- プラスチック製容器包装のマテリアルリサイクルを行っている施設は、116施設
(プラスチック製容器包装:88施設、トレイ:28施設)存在している。
(平成18年度(財)日本容器包装リサイクル協会への入札資格を持つ再生処理事業者ベース)
- このうち、一部の事業者について施設の概要を示す。
|
表 プラスチック製容器包装のマテリアルリサイクル事業者 |
|
所在地 |
プロセス概要 |
再生品用途 |
事業内容 |
再商品化 |
再生品
利用 |
|
方式 |
(株)柏エコプラザ |
千葉県柏市 |
PP、PEを選別後、造粒
処理能力は12,000トン/年 |
擬木・杭、プランター、パレット、ごみ袋等 |
○ |
3 |
○ |
JFEスチール(株)
東日本製鉄所
(水江) |
川崎市 |
高炉原料化ラインでフィルム系、ボトル系に分類したのち、粉砕、選別、造粒したものを原料として、押出成形して直接ボード化
ボードの生産能力は200万枚/年 |
再生型枠ボード(NFボード) |
○ |
2 |
○ |
福井環境事業(株) |
福井県福井市 |
ペレットを製造
処理能力は15,000t/年 |
ペレット |
○ |
2 |
|
アルパレット(株) |
福井県坂井郡 |
PP、PEを主原料としたパレットを製造
廃プラ受入能力は7,000t/年 |
パレット |
○ |
3 |
○ |
広島リサイクルセンター |
広島県御調郡 |
選別・破砕・洗浄したのち、比重分離でPE、PPを分離
(2003年度から容器包装プラスチックの再商品化能力を、年間5000tから2倍の1万tに拡大) |
ペレット、車止め、パレット等 |
○ |
3 |
○ |
(株)富山環境整備 |
富山県富山市 |
軟質系:破砕・乾燥・造粒し、ペレットミルを製造
硬質系:破砕・洗浄・乾燥しフレークを製造
ペレットミル、フレークを原料として押出成形により製品製造(一部木質混合) |
パレット、プランター、ベンチ |
○ |
2 |
○ |
三重中央開発(株) |
三重県上野市 |
2002年に容器包装プラスチック再商品化施設の改良に伴い、新たに近赤外線・光学式の樹脂選別装置を導入
一度に2種類の樹脂を指定し除去できる技術で国内初の事例 |
擬木、車止め |
○ |
2 |
○ |
|
(再商品化方式)
1: 材質別分離型
2: 成形品・フィルム類分離・比重分離型
3: 成形品・フィルム類混合・比重分離型
4: 無分離・製品型 |
|
- また、プラスチック製容器包装以外にも、産業系プラスチック(包装フィルム、通い箱等)のマテリアルリサイクルを行っている事業者の一部を以下に示す。
|
| 企業名 |
所在地 |
廃プラ需給源 |
廃プラ再生原料の用途 |
| 石塚化学産業(株) |
埼玉県北埼玉郡 |
フィルムメーカーの加工ロス、自動車バンパー、コンテナー、透析用ボトル |
エアーダクト、育苗箱、工具箱、 フィルム |
| (株)デスポーザ新横浜 |
横浜市 |
コンテナー(通い箱) |
インジェクション成形加工による分別容器(ごみ箱等) |
| いその(株) |
愛知県稲沢市 |
バッテリーケース、自動車バンパー、コンテナ、育苗箱、コードリール、パソコン、テレビのバックカバー、ガス管、自動車部品、日用雑貨、食品トレイの打ち抜きの端材など |
ペレット |
| 中村化成工業(株) |
群馬県太田市 |
コンテナー・クレート容器(飲料水・食品・工具の通い箱など)、自動車部品、パレット |
チップ、ペレット |
| (株)大誠樹脂 |
東京都江東区 |
自動車バンパー、都市ガス、堀上げ管、コンテナ、パレット、家電、OA機器等 |
ペレット |
| (有)ハイプラ |
徳島市 |
シート工場・加工場の加工ロス、野菜コンテナー、牛乳コンテナー |
加工業者、輸出業者、擬木・杭製造業者 |
| 日本プラパレット(株) |
長野県、栃木県 |
ビールケース |
パレット |
|
出典:シーエムシー「廃プラ再商品化の企業と市場の実態」(2000年2月)、
シーエムシー「2002年プラスチックリサイクル市場」(2002年6月)、各社HP、ヒアリング |
|
| 前処理の必要性 |
- 他のリサイクル技術に比べて、異物混入や汚れ、プラスチック組成等の影響を最も受けやすい技術であると考えられるため、前処理は必須。
一般的に、付加価値の高いものへリサイクルしようとすると、必要となる付加的処理も増加する。
|
| 受入条件等 |
- プラスチック製容器包装の場合は分別基準適合物であること。
|
|