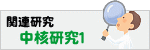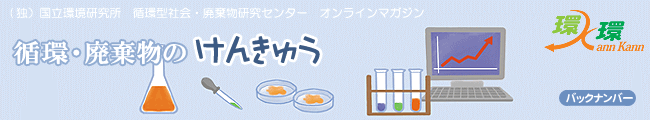
食料の消費と廃棄物
日本人の食生活の変化
 皆さんは毎日米とパンのどちらを多く食べていますか。肉と魚ではどうでしょうか。それらの食材は家庭で調理して食べていますか。それとも惣菜などの調理済み食品を購入したり、レストランなどで外食をしていますか。私たちの食生活は、社会・経済の状況や人々のライフスタイルとともに変化してきました。それでは、戦後から今日まで日本人の食料消費の状況はどのように変わってきたのでしょうか。1965年と2005年の日本人1人当たり食料消費量を図1に示しました(農林水産省平成17年度食料需給表から作成)。米、みそ、しょうゆといったいわゆる和風食材は40年前の約半分しか食べなくなったことが分かります。一方、果実、畜産物(牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、牛乳と乳製品)、魚介、油脂の消費量は増え、特に畜産物や油脂といったいわゆる洋風食材の消費は40年前の2.4倍になりました。
皆さんは毎日米とパンのどちらを多く食べていますか。肉と魚ではどうでしょうか。それらの食材は家庭で調理して食べていますか。それとも惣菜などの調理済み食品を購入したり、レストランなどで外食をしていますか。私たちの食生活は、社会・経済の状況や人々のライフスタイルとともに変化してきました。それでは、戦後から今日まで日本人の食料消費の状況はどのように変わってきたのでしょうか。1965年と2005年の日本人1人当たり食料消費量を図1に示しました(農林水産省平成17年度食料需給表から作成)。米、みそ、しょうゆといったいわゆる和風食材は40年前の約半分しか食べなくなったことが分かります。一方、果実、畜産物(牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、牛乳と乳製品)、魚介、油脂の消費量は増え、特に畜産物や油脂といったいわゆる洋風食材の消費は40年前の2.4倍になりました。
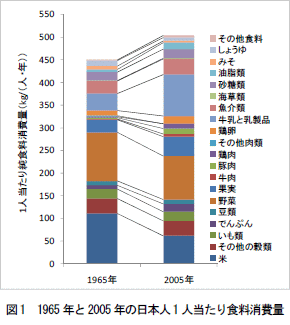
また、各家庭の食料費の中で調理済み食品と外食の占める割合を見ると、1965年には10%でしたが2005年には30%に増えています(総務省平成17年度家計調査年報から計算)。両親が共働きの家庭や単身世帯が増えたことが主な原因と言われています。さらに、私たちが食べている食材は日本国内で生産されるものもあれば海外から輸入されるものもあります。カロリーベースの食料自給率を見ると、1965年には73%でしたが2005年には40%まで減っており、国産食材よりも輸入食材の方が多くなりました(農林水産省平成17年度食料需給表から計算)。
食料消費と廃棄物
さて、前述のように食料の消費や生産の状況が変わることで、それに伴って発生する廃棄物の量や種類、その発生場所も変化すると予想されます。例えば、洋食化によって国内での米づくりが減ると、稲を収穫する時の稲わらや脱穀する時のもみ殻の発生量が減ると考えられます。また、肉を食べる量が増えると、飼育する家畜の頭数が増加するので、家畜ふん尿の発生量も増えると予想されます。また、私たちが家庭かレストランのどちらで食事をするかによって、調理くずや食べ残しなどの食品廃棄物が発生する場所も変わってきます。そこで、当研究センターでは、食料の消費や生産に伴って廃棄物がどこでどの程度発生するかを推定し、今後私たちの食生活が変化していく中で廃棄物の発生状況がどのように変わるのかを検討しています。廃棄物の発生状況を将来に渡って検討することは、今後の廃棄物管理や政策の方向性を考える重要な材料になります。
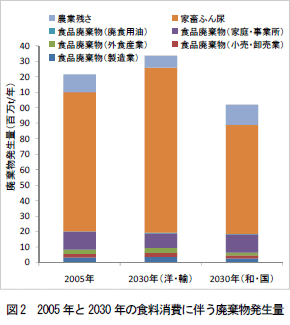 2005年と2030年の日本国内の食料消費に伴う廃棄物の発生量を推定した結果を図2に示しました。2005年を見ると、全体で約1億2000万tの廃棄物が発生し、なかでも家畜のふん尿が最も多く約9000万tでした。また、食品の加工や流通、食べ残しなどから発生する食品廃棄物は合わせて約2000万tで、半分は家庭や事業所から出る生ごみでした。
2005年と2030年の日本国内の食料消費に伴う廃棄物の発生量を推定した結果を図2に示しました。2005年を見ると、全体で約1億2000万tの廃棄物が発生し、なかでも家畜のふん尿が最も多く約9000万tでした。また、食品の加工や流通、食べ残しなどから発生する食品廃棄物は合わせて約2000万tで、半分は家庭や事業所から出る生ごみでした。
今から20年後の2030年については、私たちの食生活に関して2通りの将来像を描き廃棄物の発生量を推計しました。1つは今後も洋食化が進展し、調理済み食品と外食、輸入食材が増える傾向のまま進む将来像です。廃棄物の発生量(図2の「2030年(洋・輸)」)は全体で約1億3000万tと推計され、これから日本の人口は減るにも関わらず、廃棄物は2005年よりも増えてしまう結果となりました。特に畜産物を食べる量が増えるため家畜ふん尿が増加し、2005年の1.2倍の約1億1000万tになりました。一方、もう1つの将来像は再びかつての和食化が進み、家庭での調理、国産食材が増える方向性です。廃棄物の発生量(図2の「2030年(和・国)」)は全体で約1億tと推定され、2005年の80%程度に減ることが分かりました。米を食べる量が増えるため稲わらなどの農業残さは1.1倍に増えますが、畜産物を食べる量が減ることによって家畜ふん尿が78%に減少する結果となりました。
当研究センターでは、このような将来の食料の消費量、生産量、廃棄物発生量の推計とともに、廃棄物の発生抑制、飼料化、肥料化、エネルギー回収といった廃棄物管理の技術や政策による埋立処分量や温室効果ガス排出量の削減効果などの評価も行っています。
<もっと専門的に知りたい人は>
- 加用千裕、稲葉陸太、橋本征二、南齊規介、大迫政浩:近未来の食料需要・廃棄物フローの予測と廃棄物対策導入効果の評価、第5回日本LCA学会研究発表会講演要旨集、pp.46-47、2010