
2007年7月2日号
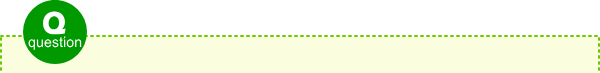
循環型社会 を作るためにリデュースが必要なものはどれでしょうか?
![[1]](img/mk1.gif) 廃棄物発生量
廃棄物発生量 ![[2]](img/mk2.gif) エネルギー消費量
エネルギー消費量 ![[3]](img/mk3.gif) 資源採取量
資源採取量 ![[4]](img/mk4.gif) 物質の総投入量
物質の総投入量

「リデュース♪、リユース♪、リサイクル♪」と軽快なフレーズを最近テレビでよく耳にしませんか?こうした広告の効果もあって、リサイクルだけでなく、リデュースやリユースといったカタカナ語もかなり浸透していると思います。しかし、"リデュース"と聞くと、リサイクルを通してゴミを減らすことをイメージする人も多いのではないでしょうか?
循環型社会を作るためのリデュースは、出たゴミを減らそう(減量)ではなく、そもそもゴミが出ないようにしよう(発生の抑制)というのが本来の意味です。 そして、リデュースが必要なのは、ゴミの発生量だけではありません。9.7億トンの国内で採取した資源を含めて、日本は年間19.8憶トンもの資源を投入しています(平成15年度)。その一部はエネルギーとして消費され、二酸化炭素というゴミになって大気中に捨てられています。また、一部は私たちが普段捨てているようなゴミになります。資源を使えばそれは必ず何らかのゴミになります。 したがって、循環型社会を作るためには、単に廃棄物の発生量を減らすだけでなく、資源採取量を含め投入される物質の総量(物質の総投入量)を減らすことが必要です。そこにはエネルギーも含まれます。


![[1]](img/mk1.gif) 〜
〜![[4]](img/mk4.gif) の全て
の全て
循環型社会を作るためのリデュースは、出たゴミを減らそう(減量)ではなく、そもそもゴミが出ないようにしよう(発生の抑制)というのが本来の意味です。 そして、リデュースが必要なのは、ゴミの発生量だけではありません。9.7億トンの国内で採取した資源を含めて、日本は年間19.8憶トンもの資源を投入しています(平成15年度)。その一部はエネルギーとして消費され、二酸化炭素というゴミになって大気中に捨てられています。また、一部は私たちが普段捨てているようなゴミになります。資源を使えばそれは必ず何らかのゴミになります。 したがって、循環型社会を作るためには、単に廃棄物の発生量を減らすだけでなく、資源採取量を含め投入される物質の総量(物質の総投入量)を減らすことが必要です。そこにはエネルギーも含まれます。

私たちの暮らしは大量の資源消費によって支えられています。リデュースの意味を、単にゴミを減らすことではなく、消費する資源の量自身を減らすことと理解すると、私たちが循環型社会に向けて何ができるか、何をすべきかを、普段とは違った角度から考えてみることができるのではないでしょうか?