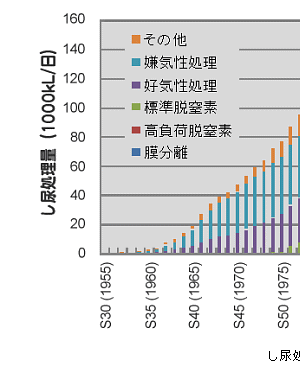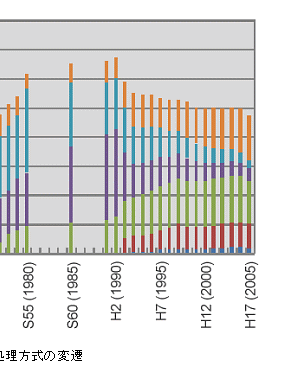第7回
第4回で戦後のし尿処理研究の奮闘ぶりをお話ししましたが、今回はそのし尿処理がさらなる困難を乗り越えて到達した先は、一体何だったのか?というお話しです。
8.し尿処理技術 その行き着く先は?
とにもかくにも増え続けるし尿を衛生処理しなければならなかった昭和30年代〜50年代、処理するのに30日以上も必要だった嫌気性消化法では間に合わなくなり、もっと早く、 もっと大量に処理できる技術開発に重点が置かれました。このため、薬品を使ってどろどろのし尿を固形物と液に分離する化学処理法や空気を吹き込む好気性消化法が開発されてきました。 しかし、これらはいずれも1次処理であり、仕上げの2次処理(一般に活性汚泥法という生物処理を用います)をしなければ放流基準をクリアできませんでした。 しかも、1次処理をした処理液も当時の技術では20倍に希釈しなければ2次処理ができませんでした。大量の希釈水の確保が大きな課題となり、希釈水を削減することも技術開発目標となったのです。

一方、昭和50年代になり経済活動や生活レベルが向上するに伴い水使用量が増大し、問題になってきたのが閉鎖性水域における富栄養化問題でした。 これに対応するためにBODあるいはCODの他にも窒素、リン、色度などに厳しい規制が設けられました。それまで先達が苦労をして開発してきた嫌気性消化法は、図のように昭和50年代までは全処理量の5割を占め、採用技術のトップランナーでしたが、厳しくなった水質規制には対応できませんでした。
しかし、わが国の技術は見事にこのハードルをクリアしました。中心的な役割を果たしたのが旧国立公衆衛生院(現国立保健医療科学院)で、そこで開発されたのが高負荷膜分離技術でした。 活性汚泥法などの生物処理法はし尿などに含まれる汚濁物質を生物に固定させ、沈殿池で固液分離して上澄みを放流します。この技術は下水などの少し薄い汚水濃度に対しては大変効果的なのですが、 し尿などの濃厚な汚水の場合には、適用が非常に困難でした。そこで膜によって固液分離ができないかという開発目標が定められました。水の中に含まれる微生物などの微粒子を分子サイズ(1mmの10,000分の1以下の大きさ)の小さな穴を持つ限外ろ過膜を使ってろ過分離する技術を使います。
昭和40年代、この限外ろ過膜は固形物がほとんど入っていない下水の2次処理水などに利用され、その処理水はビルのトイレ用水などに再利用されました。 すぐに目詰まりをして使い物にならないと最初は冷笑されていましたが、関係者の努力により確立された低圧操作技術によってこの欠点が克服され、長期運転ができるようになり大ブレイクしたのです。 この膜分離技術は、し尿中に含まれる高濃度の窒素を完璧に除去する能力も併せ持っており、希釈水が全くいらなくなったので、楽に脱色できるようになりました。膜分離技術はさらにし尿処理の現場も一変させました。 今まで開放系で処理をしていたし尿処理施設は、膜分離技術の導入により完全密閉系で処理できるようになり、"臭い、汚い、暗い"の3Kを返上できたのです。
高負荷膜分離脱窒素技術が完成するのは平成3(1991)年になります。旧国立公衆衛生院は民間企業との共同研究をとおして開発を着手してから実に6年間でこれを成し遂げました。 し尿処理分野の膜分離技術は世界に冠たる技術として脚光を浴びましたが、技術には光と陰があることを指摘しておかなければなりません。確かに、世界最高峰の技術を構築し、それまで迷惑施設のレッテルが貼られていたし尿処理施設は、 地域住民の信頼を勝ち取ることができましたが、その代償として地方自治体は高い建設と運転の費用を支払うことになりました。そのつけが国民に来たことを皆さんはご承知でしょうか? 膜分離法では、嫌気性消化法に比べて建設費用が約10倍、運転費用が約3倍になっていたのです。
話は変わりますが、平成(1990)年代に入り再び脚光を浴びるようになるまでの約15年間、わが国は嫌気性消化法の研究開発をほとんど放棄したのです。ともかく、厳しい水質規制に対応できる技術開発が急務でしたから、古くさい嫌気性消化法の改良などほとんど頭にないのは当然のことでした。 しかし、この15年の空白により、日本はヨーロッパに対して嫌気性消化法を基礎としたメタン発酵技術の進展において決定的な遅れをとることになったのです。21世紀になりメタン発酵技術は地球温暖化対策等としてのバイオガス化技術として世界から注目されるようになるのですが、 わが国はヨーロッパからこの技術を買わなければならない事態に陥っていたのでした。