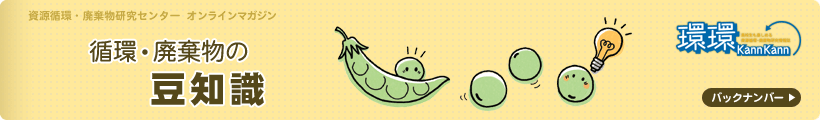
一言で固形廃棄物の処理といっても、焼却や燃料化、肥料・飼料化、埋立処理など廃棄物の性状に応じて様々な処理方法があります。どのような処理経路を辿るかによって、最終的に埋立処理される物の質や量、またはリサイクルされるものも変わってきます。日本における一般廃棄物を例にとって見ると、年間のごみ総処理量2,237万トンに対して、直接資源化量212万トン(5.0%)、中間処理量3,968万トン(93.6%)、直接最終処分量57万トン(1.4%)となっており、一般廃棄物のほとんどが中間処理されています。 中間処理とは、排出されたごみが最終処分される前に行われる処理のことで、廃棄物を減量・減容化、安定化、無害化、資源化することです。具体的には、廃棄物の性状に応じて焼却、破砕・選別、圧縮・成型、中和、脱水などの操作が行われます。ここでは、微生物を利用した中間処理、言い換えれば微生物の代謝機能を利用した固形廃棄物処理システムに注目します。この処理は食べ残し等の食品廃棄物や、下水処理によって発生する余剰汚泥などの有機物が豊富に含まれた廃棄物に有効な処理方法で、大きく分けて「好気的処理」と「嫌気的処理」の2つがあります。ここでは、好気的処理の一つである堆肥化処理(コンポスト化処理)での微生物の働きについて説明します。
中間処理とは、排出されたごみが最終処分される前に行われる処理のことで、廃棄物を減量・減容化、安定化、無害化、資源化することです。具体的には、廃棄物の性状に応じて焼却、破砕・選別、圧縮・成型、中和、脱水などの操作が行われます。ここでは、微生物を利用した中間処理、言い換えれば微生物の代謝機能を利用した固形廃棄物処理システムに注目します。この処理は食べ残し等の食品廃棄物や、下水処理によって発生する余剰汚泥などの有機物が豊富に含まれた廃棄物に有効な処理方法で、大きく分けて「好気的処理」と「嫌気的処理」の2つがあります。ここでは、好気的処理の一つである堆肥化処理(コンポスト化処理)での微生物の働きについて説明します。
固形廃棄物中で堆肥化できるものは炭水化物、脂肪およびタンパク質です。堆肥化処理では、これら3要素が微生物反応により酸化され、最終的に二酸化炭素と水が生成されます(脂肪とタンパク質は酸化されるとアンモニアも生成します)。数百度の高温状態で起きる燃焼反応と似たことが、微生物の酵素作用によって常温付近でゆっくりと反応が進むことから、堆肥化反応は「緩やかな燃焼」とも言われます。
堆肥化処理プロセスは大きく分けて「一次発酵」と「二次発酵」の2つの段階があります。一次発酵では、まず微生物により廃棄物中の炭水化物や糖類などの易分解性有機物(微生物によって分解されやすい有機物)が分解され、エネルギー源として利用されて微生物は増殖します。一般的に堆肥化処理されるごみの中には104~105個/g程度の細菌が存在していますが、一次発酵の初期段階では易分解性有機物の分解に伴い109~1010個/g程度まで急激に増殖します。この易分解性有機物の分解に伴い発生する反応熱が廃棄物層内の温度を上げ、50~80℃に達することもあります。この一次発酵前半では高温状態で生息・増殖可能な菌、いわゆる好熱性細菌がほかの細菌に比べ圧倒的に多くなります。一方で、高温状態に適さない中温菌・低温菌、病原菌や有害な寄生虫卵などは死滅または活性を失います。その後、炭水化物などの易分解性の有機物が分解し尽くされた一次発酵後半では、廃棄物層内の温度が低下し始め、それと同時にこれまで優占していた細菌の減少、真菌や放線菌等の増殖が起こり、微生物群集が多様化していきます。一次発酵は数週間程度で完了し、このまま堆肥として利用することも可能になります。
次に二次発酵では、一次発酵に続いてタンパク質、脂肪、セルロースやリグニン等の微生物分解の難しい有機物が分解されます。二次発酵は堆肥の「熟成期間」とも呼ばれ、一次発酵で分解しきれなかった有機物を、30~40℃程度で数カ月間かけてゆっくり生物分解する工程です。二次発酵中では一次発酵中と比べ、多種多様な微生物が増殖します。例えば、硝酸菌、亜硝酸菌、セルロース分解菌、真菌や放線菌が確認されており、それら微生物により、セルロース分解やタンパク質の分解で発生したアンモニアの硝化など、有機物の無機化が促進され、最終的に均質・良質で衛生的な堆肥が完成します。
 このように堆肥化処理では、順番に有機物の分解が起こり、その時々の条件に合わせて微生物が入れ替わりながら処理が行われているのです。この反応を人為的にコントロールして、廃棄物処理に利用したのが堆肥化処理施設です。様々な形式の堆肥化処理施設がありますが、送風ポンプや切返しと呼ばれる混ぜ合わせる作業によって廃棄物層内を好気状態に保ち、かつその送風量や切返し頻度を調整するなどして、微生物槽内の温度と酸素濃度のバランスをとった運転を行うことで、微生物反応を最大限利用する処理システムとなっています。以上のように堆肥化処理のような微生物を利用した資源化中間処理では、処理する廃棄物の性状に加え、その廃棄物処理に関わる微生物についてよく知ることで、効率的な処理や高品質な資源物回収が可能となります。
このように堆肥化処理では、順番に有機物の分解が起こり、その時々の条件に合わせて微生物が入れ替わりながら処理が行われているのです。この反応を人為的にコントロールして、廃棄物処理に利用したのが堆肥化処理施設です。様々な形式の堆肥化処理施設がありますが、送風ポンプや切返しと呼ばれる混ぜ合わせる作業によって廃棄物層内を好気状態に保ち、かつその送風量や切返し頻度を調整するなどして、微生物槽内の温度と酸素濃度のバランスをとった運転を行うことで、微生物反応を最大限利用する処理システムとなっています。以上のように堆肥化処理のような微生物を利用した資源化中間処理では、処理する廃棄物の性状に加え、その廃棄物処理に関わる微生物についてよく知ることで、効率的な処理や高品質な資源物回収が可能となります。
- Thomas H.Christensen, ed. Solid Waste Thechnology & Management. 2 vols. U.K.: A John Wiley and Sons, Ltd., 2010. Vol.2.
- 藤田賢二. コンポスト化技術 廃棄物有効利用のテクノロジー:技報堂出版, 1993.
